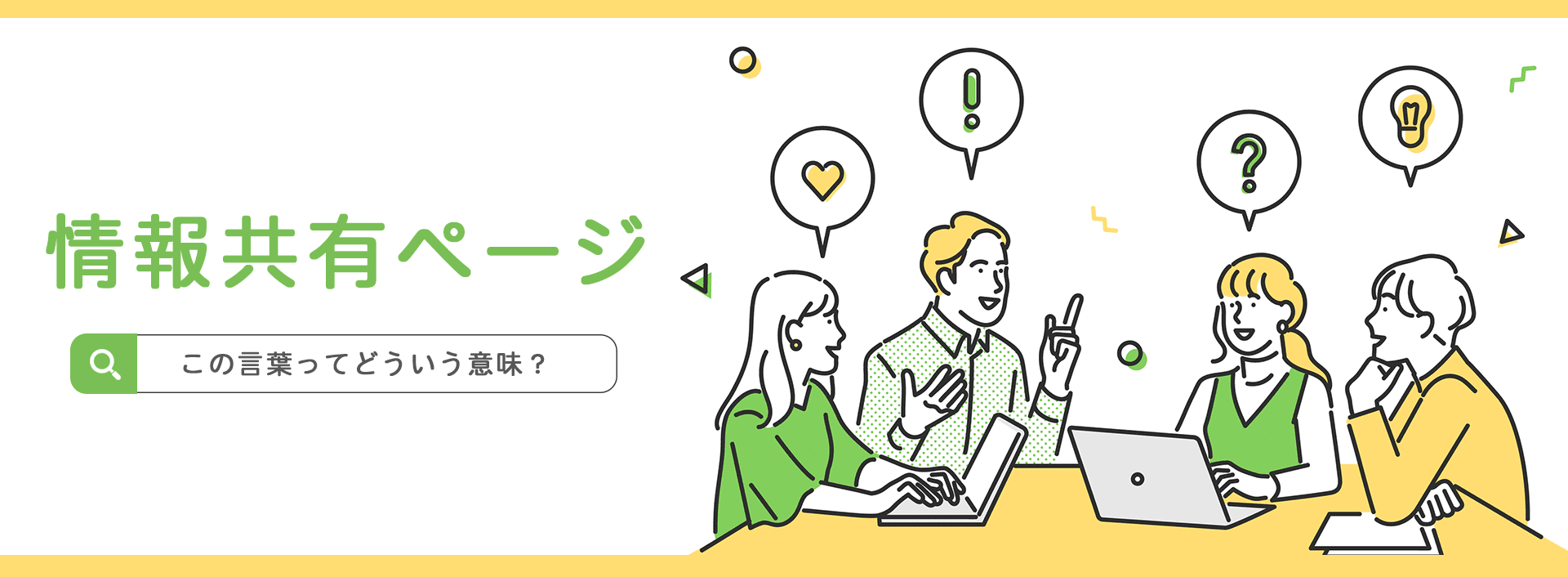
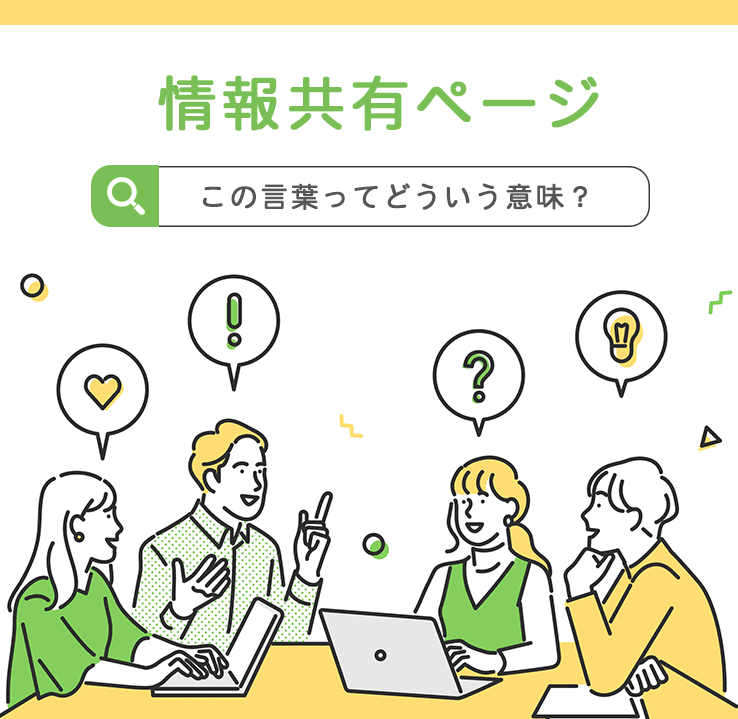
各種保険について
社会保険
健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つをまとめて『社会保険』と呼びます。労働者は3つすべて負担義務があります。
企業に勤めている会社員や、条件を満たしている短時間労働者(アルバイトやパートなど)が加入する保険です。健康保険は勤め先の会社を介して加入します。配偶者(事実婚などの内縁者を含む)や三親等以内の親族も加入することが可能です。
介護が必要になった高齢者を、社会全体で支えるしくみが介護保険制度です。40歳から保険料を支払うことが国民に義務付けられています。
会社員や公務員が加入できる年金制度です。アルバイトやパートタイマーの方でも一定の要件を満たした場合には厚生年金に加入することになります。
労働保険
雇用保険・労災保険の2つをまとめて『労働保険』と呼びます。労働者は雇用保険のみ負担義務があります。
労働者が失業した際や職業に関する教育訓練を受けた場合などに、給付が受けられる制度です。受けられる給付は失業等給付をはじめ、育児休業給付や再就職手当など生活や雇用の安定、再就職の資金として役立てることができます。
労働者の業務災害や通勤災害などによるケガや障害などに対して、保険給付を行うことを目的とする保険制度です。労災保険料は会社が支払うため、労働者が個人負担することはありません。
その他
その他の制度
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障する制度です。病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。手続きはご本人が行います。(次項目参照)
退職した後も引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。手続きはご本人が行います。(次項目参照)
母体保護の見地から認められている休業制度です。 雇用形態に関係なく、どなたでも取得できます。産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、出産予定日よりも実際の出産日が後の場合はその差の日数分も産前休業に含まれます。産後は8週間以内です。健康保険及び厚生年金保険料は免除されます。手続きは企業が行いますが、産前は医師の診断書・産後は出産証明書が必要になる場合もあります。どんな書類が必要になるか、企業に確認しておきましょう。
お子さんが満1歳(保育所に入所できない等の場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日まで認められている休業です。取得には条件があります。(次項目参照)父・母1人ずつが取得できる休業期間(母親は産後休業期間を含む)の上限は1年間ですが、一緒に育休を取得する場合は、1歳2ヶ月まで取得期間が延長されます(パパ・ママ育休プラス制度)。健康保険及び厚生年金保険料は免除されます。手続きは企業が行います。
制度の申請方法
条件・書類・方法・注意点
下記4つの条件すべて必須となります。
- 業務外の病気やけがで療養中であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
- 休職期間に給与の支払いがないこと
【必要書類】
傷病手当金を申請するには傷病手当金支給申請書が必要です。この申請書は、以下の書類4枚1組となっています。
- 被保険者記入用:2枚
- 事業主記入用(会社が記入):1枚
- 療養担当者記入用(医師が記入):1枚
【手続き方法】
- 傷病手当金支給申請書を印刷し「被保険者記入用」を作成する
まずは、業務外の病気やけがで働けない状態にあることを会社に報告し、長期欠勤する旨を伝えます。その後、保険者(協会けんぽや保険組合)のページから傷病手当金支給申請書を印刷し、「被保険者記入用」の2枚を作成しましょう。 - 医師に「療養担当者記入用」の記入を依頼する
医師に傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入用」の記入を依頼します。これは、休職期間中に「働けない状態」であったことを証明してもらう書類です。書類作成に2週間程度かかることもあるので、早めの依頼が肝心です。 - 会社に「事業主記入用」の記入を依頼する
会社に傷病手当金支給申請書の「事業主記入用」の記入を依頼します。これは、休職期間中に給与が支払われていないことを証明してもらう書類です。 - 傷病手当金の支給申請をする
4枚の書類が揃ったら、保険者(協会けんぽや保険組合)へ傷病手当金の支給申請をします。支給申請は会社を経由して行うのが一般的ですが、本人が直接郵送しても問題ありません。申請が遅れると支給日も遅れてしまうため、手当金をできるだけ早めに受給したいという場合は迅速な申請を心がけましょう。
【注意点】
- 申請してからお金がもらえるまで数週間はかかる
- 申請は事後が基本
- 長期休業の場合は1ヵ月ごとに申請する
- 金額は個人それぞれ異なる
下記2つの条件が必須となります。
- 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
【必要書類】
こちらのページから任意継続被保険者資格取得申出書を印刷してください。退職日が確認できる書類は任意ですが、あれば早めに被保険者証の発行が可能になります。
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 退職日が確認できる書類(任意)
退職証明書のコピー、雇用保険被保険者離職票のコピー、健康保険被保険者資格喪失届のコピー、事業主または公的機関が作成した資格喪失の事実が確認できる書類、申出書の健康保険資格喪失証明欄(事業主記入用)への記載のどれか
【手続き方法】
- 任意継続被保険者資格取得申出書の記入例を参考に記入
- 申請書を健康保険組合にご自身で送付
退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に申請書が到着していることが必須となります。1日でも過ぎた場合は、法律上受付することができません。
【注意点】
- 保険証は約2~3週間後に届く
- 退職等された時の標準報酬月額(上限は30万円)によって保険料が決定される
- 任意継続の保険料は全額自己負担
- 国保に加入すると任意継続へは切り替えられない
下記3つの条件すべて必須となります。
- 同じ事業主に過去1年以上雇用されていること
- 子どもが1歳になった後も雇用される予定があること
- 所定労働日数が週2日以下でないこと